スヘイルさんに聞きました!
オレンジワインの
これまでとこれから。

日本でも急激に一般化しているオレンジワイン。
このオレンジワインと言う、新しく確立されたジャンルを、現時点で最も深く知る方にお越し頂きました。日本人が未踏のワイン産地を含め、世界15か国から日本へワインを輸入。オレンジワインに関する本の販売に携わるなど、このジャンルにおける最新の情報をもつ第一人者のスヘイルさんです。色々と伺っていきましょう。
その前に…オレンジワインの概要
日本のワイン市場でも10年程前から見るようになりましたが、当初は自然派の生産者が作る特殊な(そしてその多くは価格に見合わない)ワインが中心となっており、一部のマニア用ジャンルと考えていました。
ただ、その当時からペアリングに対する幅の広さが感じられ、その動向は気になる存在でした。
コロナ禍に突入する手前頃から、ようやく日常価格帯のオレンジワインが登場し、一気に一般消費者へも広がりました。
待ちかねていた事もあり、カーヴドテールでもついつい仕入れ、店頭には100種類近いオレンジワインが並んでいました。
今は、その味わいにも系統が現れ、次第にまとまりを見せている事から、それぞれの系統で最良なものをセレクトして絞り込みする時代に入っています。
特にオーストリア、フランス、イタリアなど自然派と呼ばれる生産者が多いエリアからは、地域、品種を問わず、また価格帯にも広がりが見えるようになりました。
また同時に、ジョージアや、一部のポルトガルなど、伝統的にオレンジワインを作り継けてきた産地のワインに注目が集まっています。

スヘイルさんがオレンジワインの最新動向に精通されている理由を教えてください。
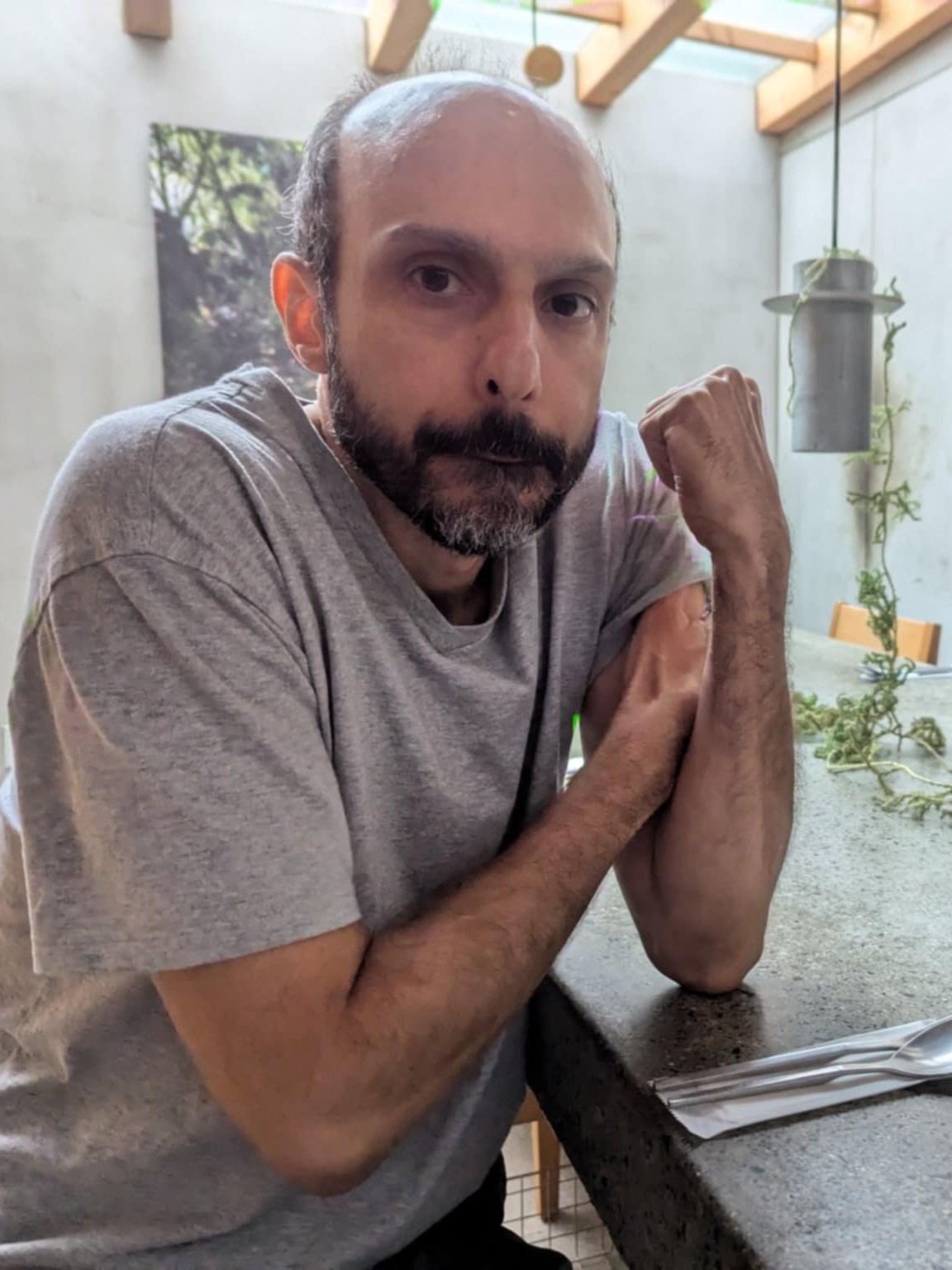 スヘイルさん
スヘイルさん
私たちの理念に沿って、常にあまり知られていない“穴場的”なワインを探し求めているのですが、これが自然と(自然派ワインならではのダジャレではありません)オレンジワインの世界につながっていきます。
他の多くのインポーターが”つい”見て見ぬふりをしてしまうカテゴリーでもあります。
さまざまな地域や忘れられたスタイルを探るうちに、オレンジワインは繰り返し現れてきます——そして私はそれを見過ごさないようにしています。
アンバーワイン(一般的にはオレンジワイン)とは何でしょうか?簡単にご説明いただけますか?
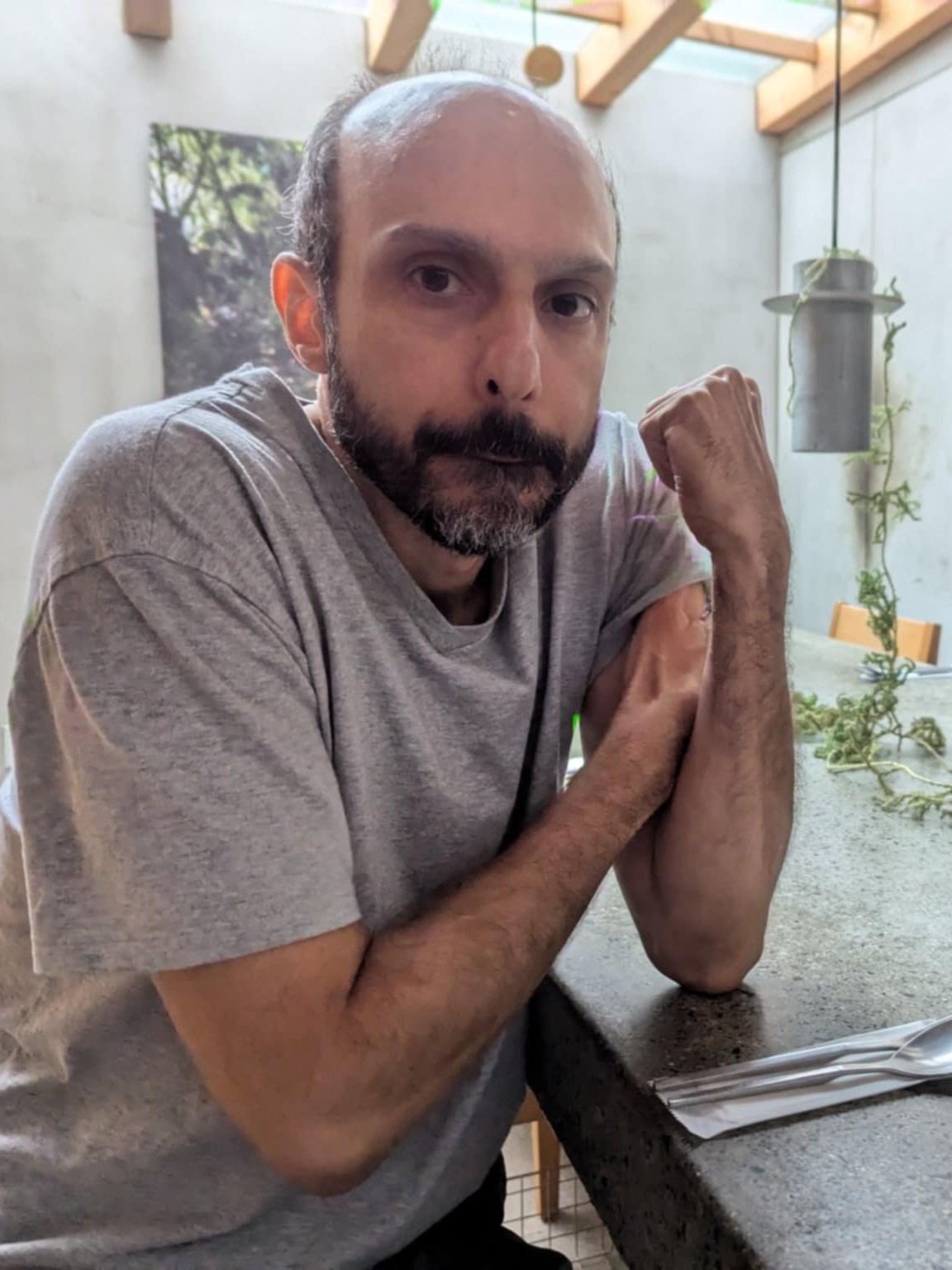 スヘイルさん
スヘイルさん
簡単に言えば、白ブドウを赤ワインと同じ製法で造ったワインです。
つまり、果汁を果皮や場合によっては茎と一緒に発酵させます。
この“スキンコンタクト”によって、ワインに琥珀色やオレンジ色の色調、品種のアロマ芳香特性、そして独特の構造やタンニンが生まれるのです。
オレンジワインの味わいには、どのような共通点や特徴がありますか?
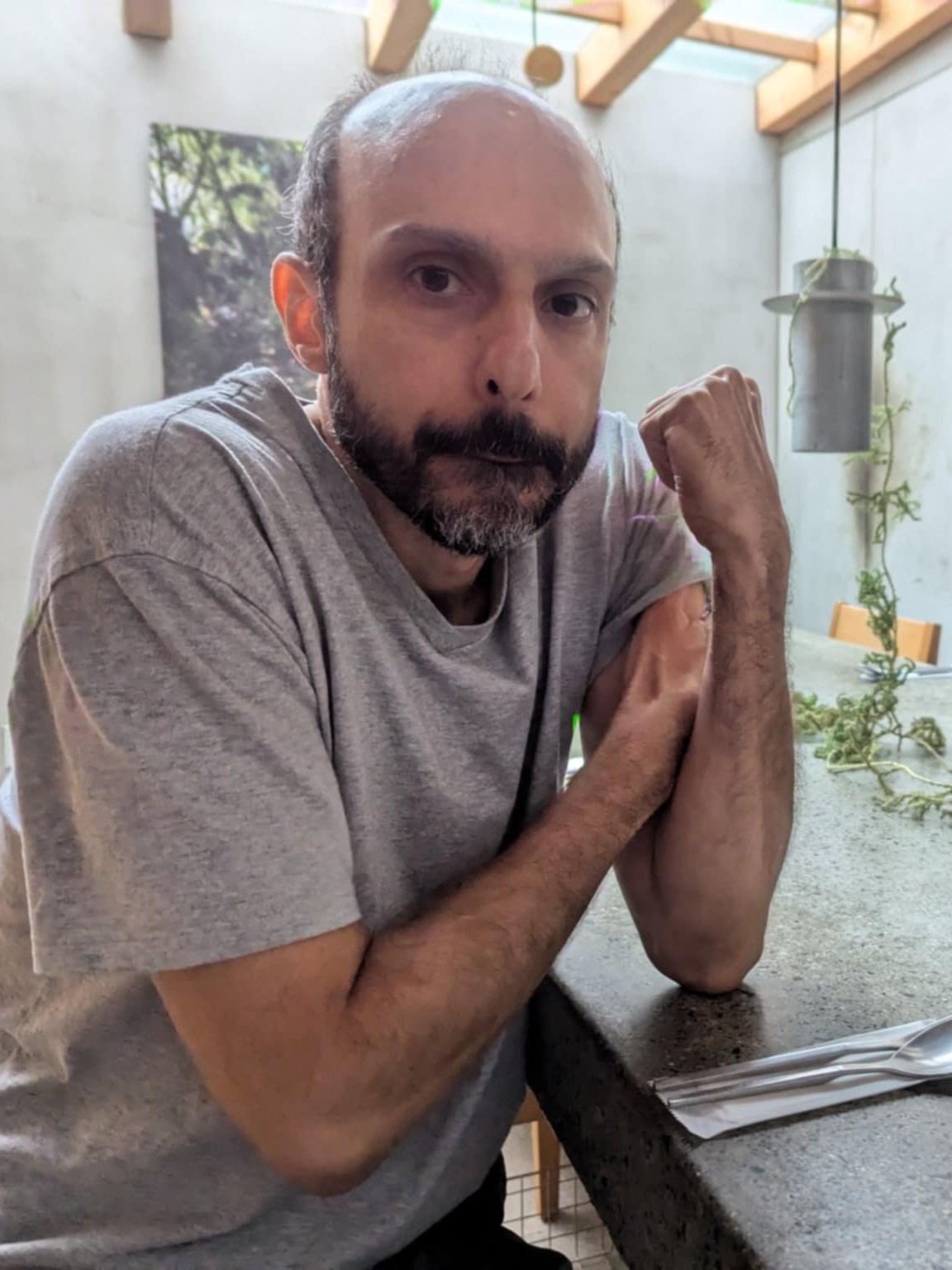 スヘイルさん
スヘイルさん
これは一言で答えるのが難しい質問です。
というのも、赤・白・ロゼについてこのような質問をされることはまずありませんよね?
ブドウ品種、産地、醸造手法によって味わいは大きく異なります。
とはいえ、オレンジワインはまだ新しいカテゴリーなので(すでに確立されたカテゴリーではありますが)、共通する特徴もあります。
たとえば、しっかりしたテクスチャー、穏やかなタンニン、旨味や紅茶のような風味。
ドライアプリコット、オレンジピール、ハーブ、ナッツのような風味を感じることもあります。
特に魚料理(魚卵なども)のようにワインとのペアリングが難しい料理にも合わせやすいのが魅力です。
ただし、これらの特徴から完全に外れるオレンジワインも存在します。
なぜオレンジワインは世界的なトレンドになったのでしょうか?
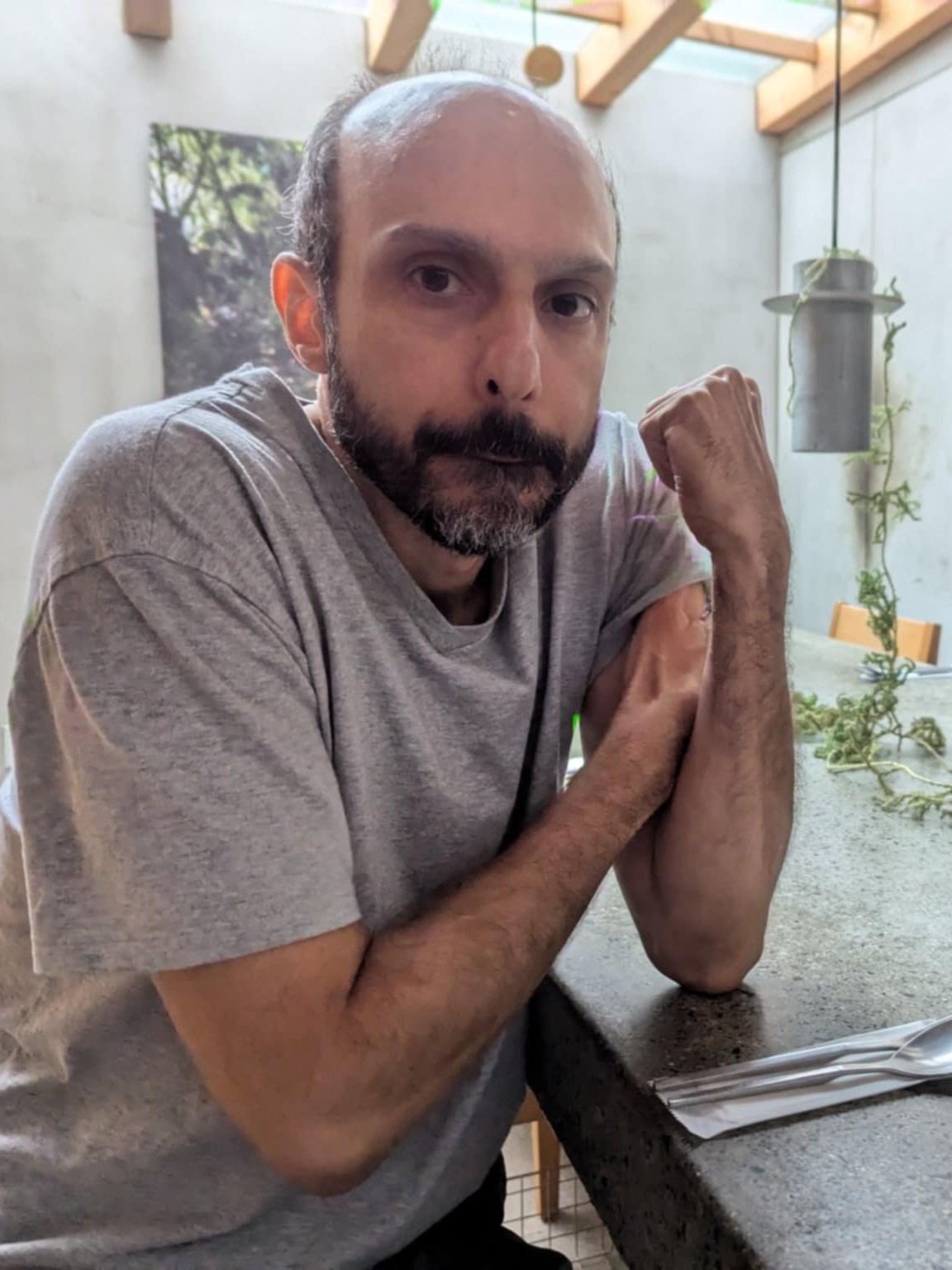 スヘイルさん
スヘイルさん
実は、この製法が第二次世界大戦以降ほとんど姿を消していたこと自体が不思議と言えます。
今のいわゆる“トレンド”は、むしろ歴史的な正当性を、より現時代に戻ってきたような動きだと感じています。
自然な製法や地域性への回帰、エコ意識の高まりといった流れとちょうど一致しました。
多くのオレンジワインは人的介入が最小限なので、その土地の個性がしっかり表れています。
さらに、ラベルデザインにも型破りな面白さがあり、主流ワインの“真面目さ”とは一線を画していて、それも魅力のひとつです。
オレンジワインの発祥はジョージアだと言われていますが、それについてどう思われますか?
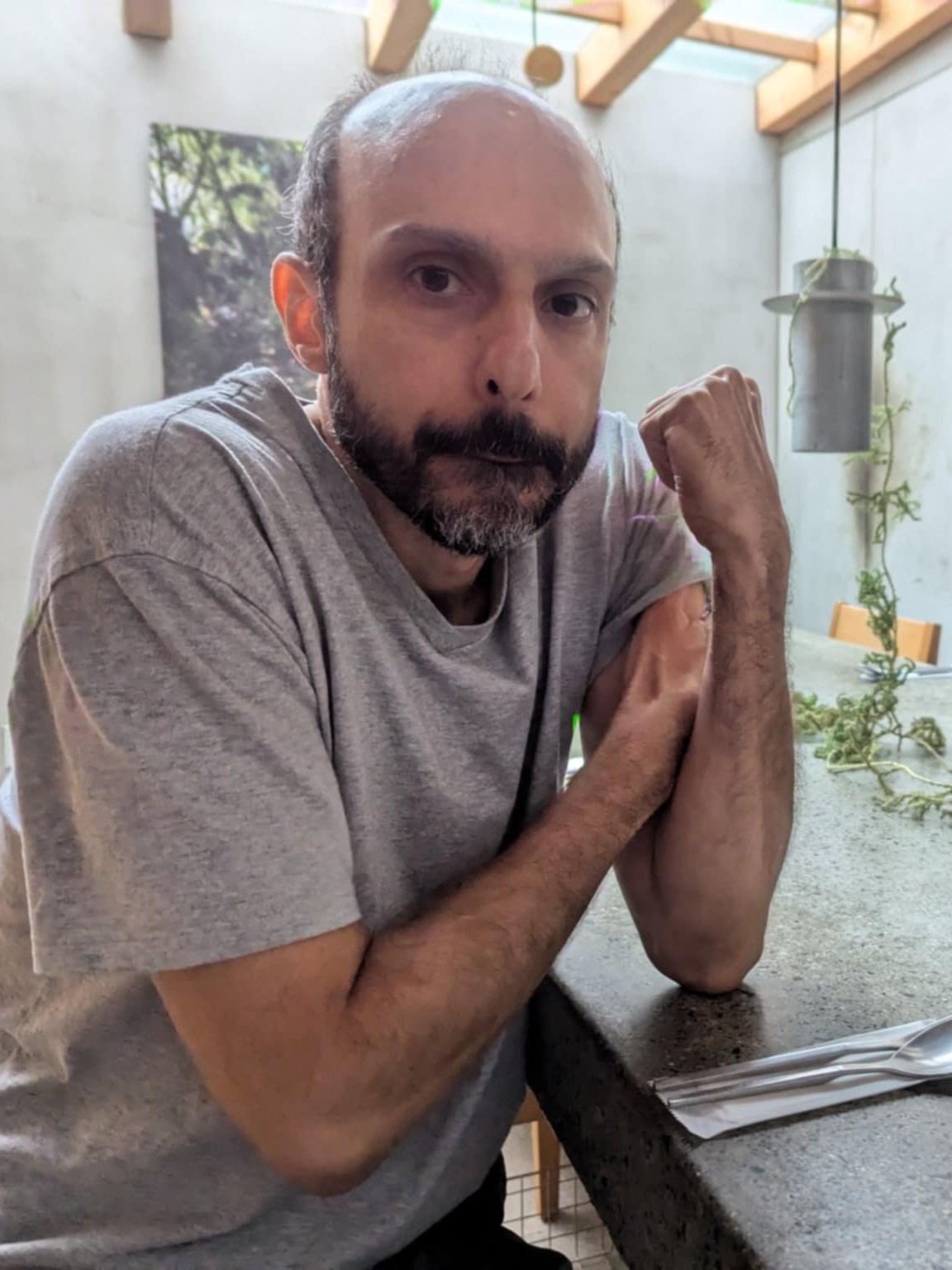 スヘイルさん
スヘイルさん
ワインの起源がジョージアにあると広く認められている理論上は、オレンジワインの起源もそこにあると考えるのが自然です。
スキンコンタクトの技法は、ワイン造りそのものと同じくらい古くから存在しています——昔はブドウの色に関係なく、果皮ごと発酵させていましたからね。
近東など他の地域にも同様の伝統はありますが、ジョージアの特徴はその「継続性」にあります。
たとえば、ポルトガルのターリアワイン醸造も2000年以上の歴史がありますが、ジョージアは8000年にわたってその技法を守り続けてきました。
ちなみに、ジョージアの生産者に「オレンジワインを試飲させてください」と言うと、きっと肩をすくめるでしょう。
彼らにとってはただの“ワイン”ですから。
そして呼び方も「アンバー」なのが無難です。
これは一過性のブームでしょうか?今後の可能性についてどう思われますか?
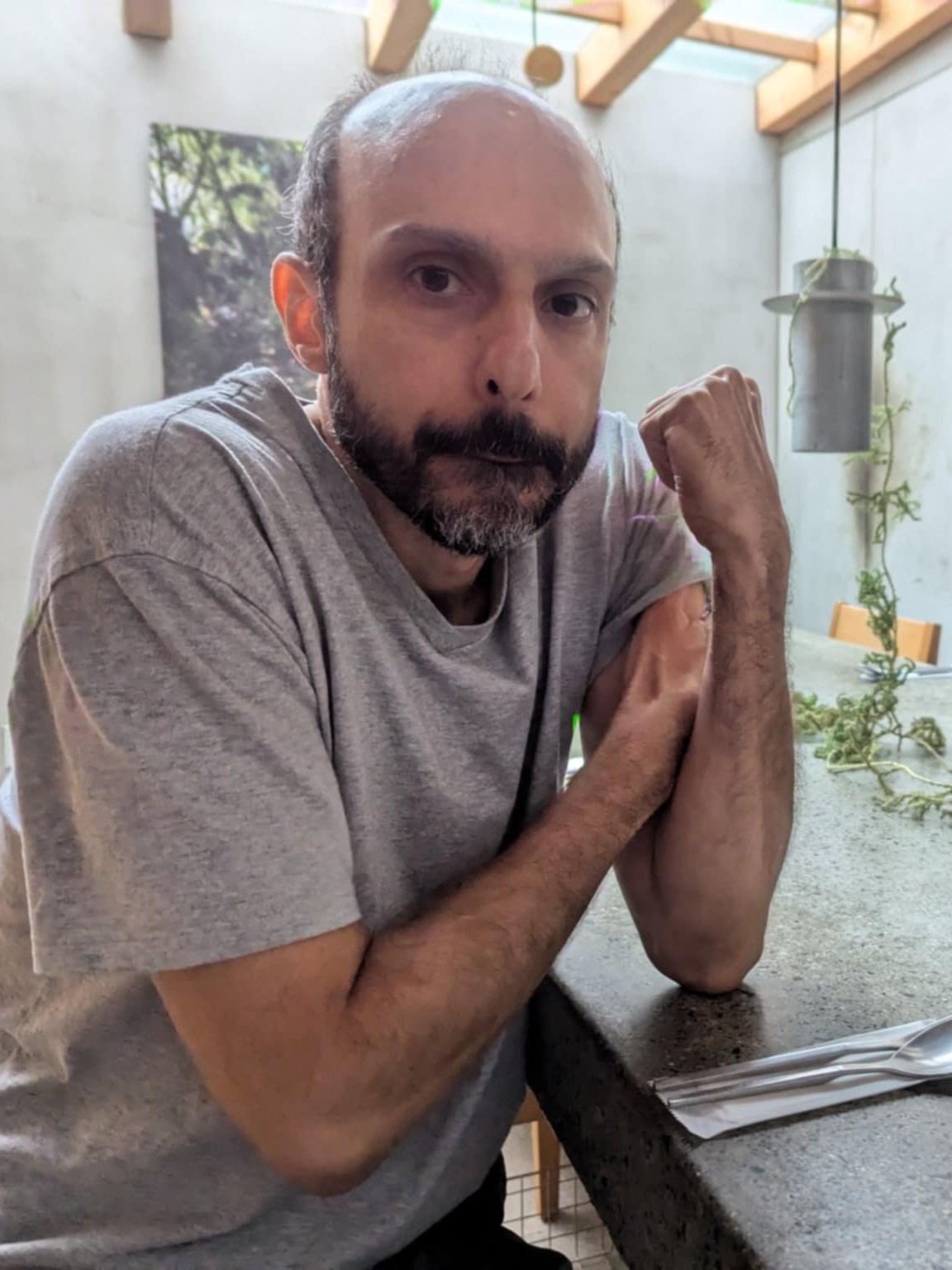 スヘイルさん
スヘイルさん
オレンジワインは、今後も定着していくと思います。
むしろ一度消えてしまっていたことの方が不自然です。
なぜ赤ブドウは果皮ごと発酵させるのに、白ブドウは果皮を取り除くのが当たり前になったのでしょうか?
ブドウの“白”や“赤”という分類も実は曖昧で、実際にはさまざまな色の品種があります。
サイモン・ウルフ氏が2018年に『Amber Revolution』という本を出版した頃、オレンジワインはまだ限られた地域でしか造られていませんでした。
今では、ほぼ世界中のワイン産地でスキンコンタクトのスタイルが取り入れられています。
オレンジワインに適した産地やブドウ品種で、今後注目すべきものはありますか?
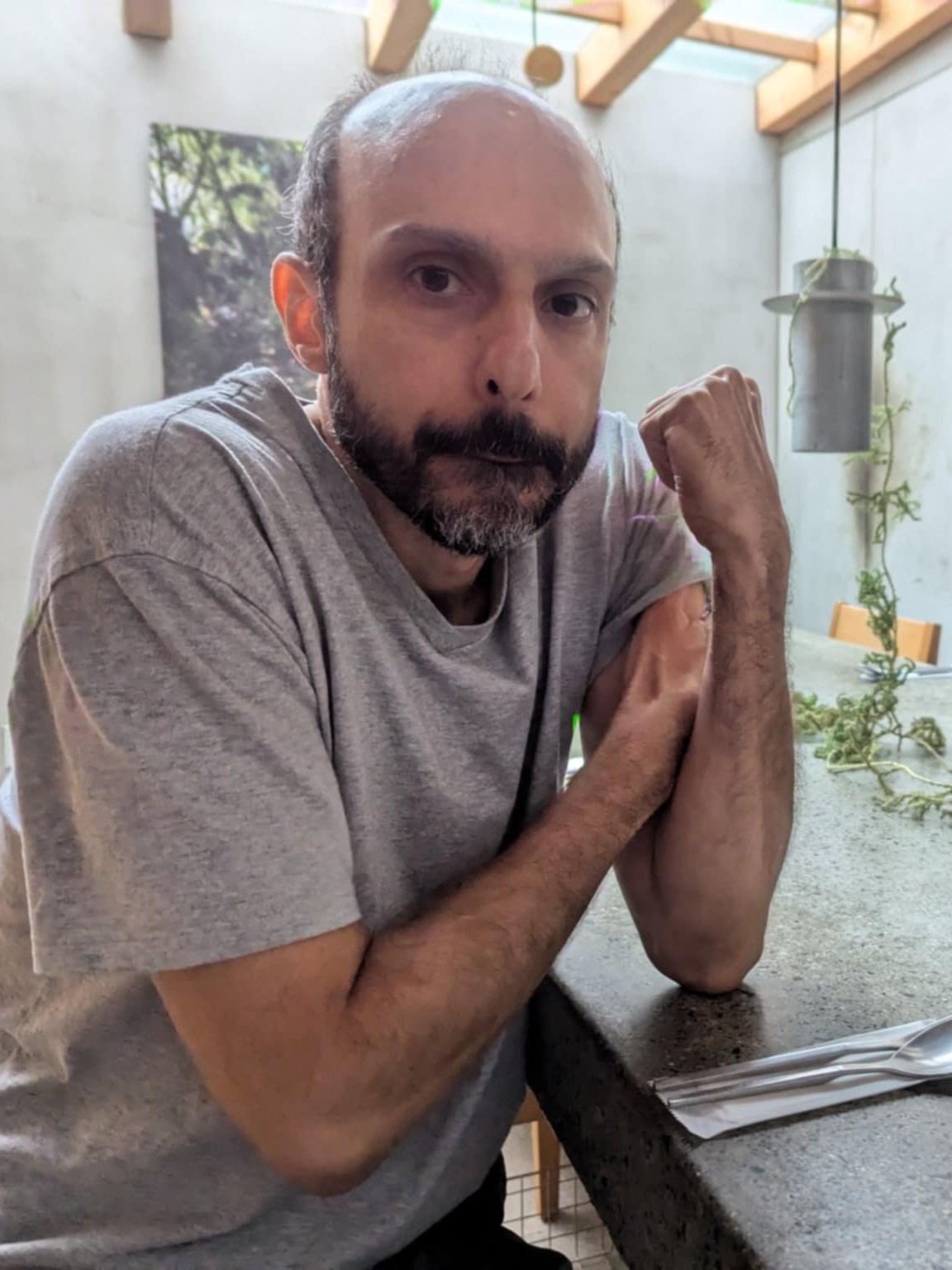 スヘイルさん
スヘイルさん
こういった質問には、できれば答えたくないのが本音です(笑)。
オレンジワインは特定の産地や品種に限定されるものではありません。
あくまで“技法”であり、上手にこの醸造方法を使えばどんな土地や品種でも素晴らしい結果が生まれます。
とはいえ、せっかくなので自社ワインの宣伝も兼ねて挙げておくと、アグリピオティス(ギリシャ)、モロカネラ(キプロス)、チティストヴァラ(ジョージア)、オベイデ(レバノン)、そしてPIWI(耐病性品種)(オランダなど)など、あまり知られていない品種から驚くようなオレンジワインが生まれています。
話題は少し逸れますが、15か国から個性的なワインを輸入されているスヘイルさんに伺います。気候変動の影響を受け、今後注目すべき国はどこだと思われますか?
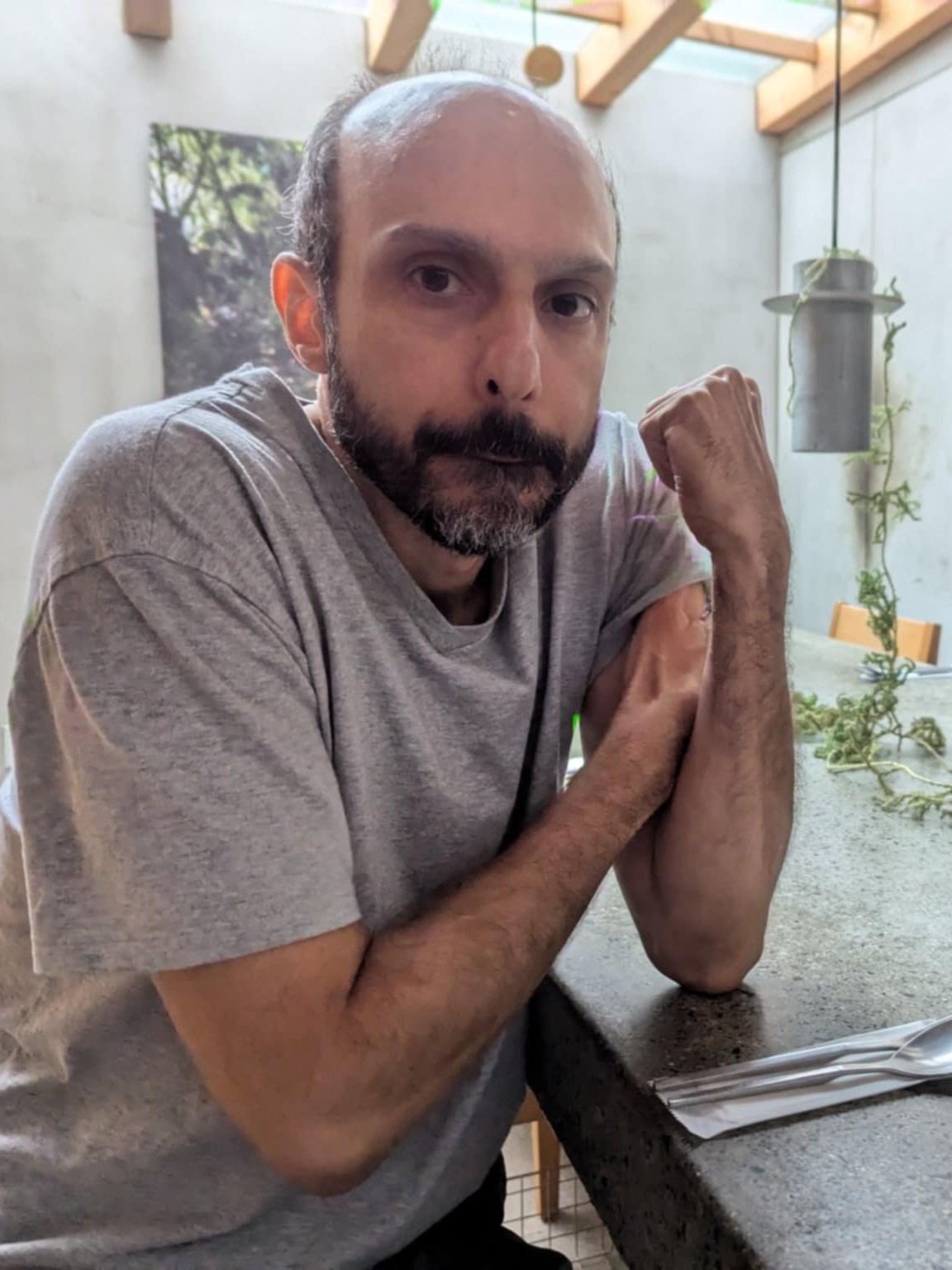 スヘイルさん
スヘイルさん
はい、今では15か国になりました 😊。
基本的には、これまで気候的にブドウ栽培が難しかった高緯度や高地の地域が今後注目されるでしょう。
また、従来のワイン産地でも、気候に適応するために栽培される品種が変わってくると思います。
ワイン業界は他の農産物と比べて保守的なところがありますが、現実を直視する必要があります。
変化に対応できないところは厳しい状況に直面するでしょう。
伝統を重んじるシャンパーニュ地方でさえ、いまや耐病性品種(PIWI)の試験栽培を始めているのですから。
今後どの地域が時代に適応できるか、注目ですね。
もっと詳しく知りたい!
【オレンジワインの祖「ジョージア」における伝統的なアンバーワイン】
ジョージアにおけるオレンジワインの作り方は、非常に伝統的で独特です。主な特徴は、ブドウの皮や種、時には梗も一緒に発酵させること、そしてクヴェヴリと呼ばれる粘土の壺を使用することです。以下にその手順を追って説明します。
1:ブドウの収穫 (Rkatsiteli, Mtsvaneなどの白ブドウ品種)
ブドウが最適な熟度に達した時期に手摘みで収穫されます。主にジョージア固有の白ブドウ品種、特にルカツィテリ(Rkatsiteli)やムツヴァネ(Mtsvane)が使われますが、他の品種も使われます。
2:除梗・破砕
収穫されたブドウは、伝統的にはサツナヘリ(Satsnakheli)と呼ばれる大きな木製のプレス機で処理されます。サツナヘリは通常、くり抜かれた巨大な木の幹で作られており、ブドウはそこに投入され、素足で踏みつけられて優しく破砕されます。この伝統的な方法により、ブドウの種子を傷つけることなく果皮から果汁を抽出し、苦味の少ないワインに繋がると言われています。この過程で、ブドウの梗は通常、手作業で取り除かれますが、一部の伝統的な作り手はあえて残すこともあります。
3:クヴェヴリ(Qvevri)への投入
除梗・破砕されたブドウの果汁、果皮、種子、そして場合によっては梗の一部が、地下に埋められたクヴェヴリと呼ばれる大きな粘土の壺に直接投入されます。クヴェヴリは蜜蝋などで内側がコーティングされており、通気性を保ちつつも密閉性が高いのが特徴です。 この皮や種との接触期間が、オレンジワインの特徴的な色合いとタンニン、風味の形成に不可欠です。
4:自然発酵(野生酵母)
クヴェヴリに投入されたブドウは、外から酵母を加えることなく、ブドウの果皮に付着している野生酵母によって自然に発酵が始まります。 発酵中、果皮や種は果汁の表面に浮き上がり、キャップ(果帽)を形成します。伝統的には、このキャップを日に数回、手作業でかき混ぜて果汁と接触させます。これにより、色、タンニン、アロマが効率的に抽出されます。
5:マセラシオン(皮との接触)
アルコール発酵が完了した後も、ワインは数週間から数ヶ月、長い場合は半年以上、果皮、種、そして残された梗と共にクヴェヴリの中で「マセラシオン」と呼ばれる期間を過ごします。
この長いマセラシオン期間が、オレンジワインの独特な琥珀色、複雑なアロマ(ナッツ、ドライフルーツ、紅茶、ハーブなど)、そして独特のタンニンによる骨格を形成します。
6:澱引き(デキャンタージュ)
マセラシオン期間が終了すると、クヴェヴリの底に沈殿した固形物(澱)からワインを分離するため、別のクヴェヴリやタンク、樽に移し替えられます。伝統的な方法では、この澱引きも重力に任せてゆっくりと行われます。
7:熟成
ワインはその後、数ヶ月から数年間、クヴェヴリやオーク樽、またはステンレスタンクで熟成されます。クヴェヴリでの熟成は、ワインに独特のミネラル感と微細な酸素供給による複雑さをもたらします。
8:ボトリング
最終的な熟成期間を経て、ワインは濾過をほとんど、あるいは全く行わずにボトリングされます。これにより、ワイン本来の風味や成分が最大限に保たれます。また、亜硫酸(SO2)の使用も最小限に抑えられるか、全く使用されないこともあります。
この伝統的な製法により、ジョージアのオレンジワインは、その豊かな色合い、複雑な風味、そしてしっかりとした骨格を持つ、他に類を見ないワインとして世界中で注目されています。
-

【参加者募集】 パウロさんを講師に招いて「ポルトガル・ワインセミナー&試飲会」開催:3月20日 /イベント
¥1,818 -

【予約・西宮北口本店引き取り限定】 パステル・デ・ナタ(エッグタルト)お引渡し:3月14日㈯ /イベント
¥1,389 ~ ¥2,778 -

ヴァルポリッチェラ リパッソ ファザン /Ripasso fazan/イタリア赤
¥5,454 -

アマローネ デッラ ヴァルポリッチェラ2019 ファザン /amarone fazan/イタリア赤
¥10,909 -

【オンライン限定】トップディッシュ カチャトーラ【お惣菜・真空パック】※
¥926 -

【オンライン限定販売】トップディッシュ 牛タンシチュー【お惣菜・真空パック】※
¥1,388

